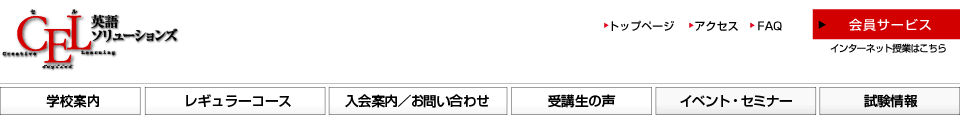
「英語総合力養成講座」~英検準1級、そして1級へ~
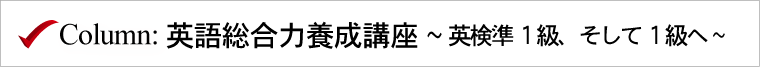
|
■第5回:英語を「話す」~日常英会話から一歩先にむけて「話すインプット」を
CEL英語ソリューションズ 最高経営責任者
曽根 宏 論理立てて、主張し意見を述べる難しさ(続き)相手に分かりやすく、ゆっくりと話した場合、この分量で約2分になるはずです。一度ご自身で朗読なさってみてください。これだけの主張を、すぐに、しかも英語で話すことはとても難しいことでしょう。 ちなみに、2004年11月の英検1級2次試験で出題されたトピックは、上記のトピックに加えて、午前組と午後組あわせて以下の9つです。
さすがに、実用英語技能検定の最高レベルの1級の最終試験だけあって、スピーチトピックとしては、いずれもタフな題材ばかりであることは一目瞭然です。このような話題を、準備時間があるとは言え、それもたった1分間、事実上impromptuでスピーチするのは、ふだんから「論理立てて、口頭で英語を話す」習慣がない、また特別にそのような訓練を受けていない方には、至難の技ではないでしょうか。 それより何より、まずは、このような社会、経済、政治、国際問題について、日頃から幅広くアンテナを伸ばして情報を収集し、問題意識を醸成していることが前提条件となります。 つまり、英語である特定の内容について「話す」ためには、以下の過程が必要になってきます。
上記2)の段階までは、母語である日本語で行った方が効率が良いでしょう。ということで、上記練習問題のトピックについて、まずは「日本語で」2分間スピーチしてみてください。母語で話せないことを、外国語である英語で話すことなどできないことは、あまりにも自明ですから。 私どもが作成した英文のサンプルスピーチの内容に沿うならば、以下のような日本語になるでしょう。 「国際化の進展とともに自由貿易が進み、ここ日本では世界中の食物を楽しむことができます。その上、食物は、私たちの食卓に届く前に、様々な形で加工されています。このような現状を踏まえますと、私たちは、食品安全基準が十分に満たされているかどうか、真剣に考える必要があります。残念ながら、現状では、それは十分とは言えないでしょう。 これまで日本政府は、国民保護の視点からある程度は食品産業を規制してきました。しかし、以下に述べる2つの事例を見てもわかるとおり、その規制は不十分であったと言わざるをえません。 まず、大手乳業メーカーが、腐敗した乳製品をそれと知りながら販売した事件がありました。2つ目は、いわゆるBSE、狂牛病問題です。これらの問題に対して、日本政府は、消費者の安全を十分に確保するために必要な施策を講じたとは到底思えません。 次に、日本に輸入される食品の問題があります。化学薬品で汚染された食物も問題ですが、さらに深刻なのが遺伝子組み換え食品、いわゆるGM食品の輸入問題です。現在の制度では、遺伝子組み換えで生産された原材料が5%未満の場合に限って、「非GM食品」と認定されています。GM食品を一切食べたくないと思っても、このような曖昧な基準では、消費者はどの食品を選べば良いか途方に暮れてしまいます。 以上、私が、日本の食品安全基準は依然として不備であると主張する理由がお分かりいただけたかと思います。今後、日本政府が、信頼するに足る食品の安全を保証するためにも、より厳格な食品安全基準を定め、より綿密な食品検査を実施することを願ってやみません。」 前述した英検1級2次試験スピーチの他の9つのトピックでも、同じように、英語のスピーチを組み立ててみてはいかがでしょうか。情報収集から始まって、自分の意見形成、英語の文章作成と、とても刺激的な知的作業になること請け合いです。 |