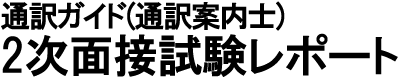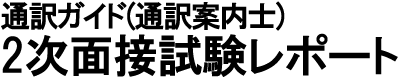
受講生6 女性
試験の様子
15:30集合、16:00移動、17:00本番開始。試験官は、米・英(?)人男性(50代?)、日本人男性(50代?)の2名。
質問内容
A: (ドアをノックして)Good afternoon.
N: Good afternoon.
J: Have a seat.
質問1. どこにお住まいですか?
A: 神奈川県の横浜市からきました。
質問2. 私が旅行者だとして、横浜のどこを案内しますか?
A: 横浜の観光地の多くが横浜港を中心にあります。 公園やショッピングモール、チャイナタウンなどありますが、外国からのお客さまにはあまり興味を持たれるところではないかもしれません。そこで日本庭園「横浜三渓園」をご案内したいと思います。バスで港からは20分ほど、横浜駅東口のバス停からでしたら30分ほどの所にあります。池や築山、三重塔などがあります。
質問3. (名前の姓についての質問)
質問4. 日本人の平均寿命はどのくらいですか?
A: 女性は86歳余り。男性は79歳(76歳と答えたかも?)位です。
質問5. そんなに男女差があるのですか? なぜ、女性はそのように長生きで、男性はそうではないのですか?
A: 今、70代、80代の女性は家庭にいた方が多かったからでは。
もちろん、今は多くの女性が働いています。 それに比べ、男性は社会に出て働き、ストレス・プレッシャーがより多かったのだと思います。 また、女性の方が、健康により気を配ったのではないでしょうか。
質問6. 1964年の東京オリンピック以来、東京はどのように変わりましたか?
A: ん~、そうですね。人口が増えました。都市部での人口が集中しています。近年、美術館など建物が新たに建設されました。来年5月には、「東京スカイツリー」が完成される予定です。
質問7. 松尾芭蕉の俳句を何か知っていますか?
A: 「古池や蛙飛び込む水の音」 これは訳すると An ancient pond. A frog jumps in. The sound of the water. これはドナルド・キーン氏の訳です。 キーン氏はアメリカ人で最近日本の国籍を取られました。
(質問者:知っています。)
質問8. あなたはこの俳句に何を感じますか?
A: peace and serenity を感じます。
質問9. 俳句は好きですか?
はい、趣味のひとつです。昨年の秋から勉強しています。
質問者:ありがとう。
日本人試験官 :これから、日本語で質問します。日本語で答えて下さい。
質問1. あなたは観光ガイドとしてどのようなことが大切だと思い
ますか?
A: 旅行者が安全には気を付けたいと思います。 昨年、たまたま米国の旅行者を案内する機会がありましたが、 1人が高齢者で、とても足元に気を付けました。 また、観光地の情報は本などで知ることはできると思いますが、 ガイドとして、直接にいろいろ旅行者に伝えることが出来たら 良いと思います。コミュニケーションを大切にしたいです。
試験官 これで終わります。
A: 「ありがとうございました。」
試験を終えて
CELでの模擬面接を経験もあり、極度の緊張をすることは
ありませんでした。ただ、どれも不十分な回答が出来なかったことは自覚しています。
また、ジェスチャーを交えて説明した記憶がないので、表現力
の点でどうであったのか不安が残ります。相手の目を見て答える
ことは出来たと思います。
最後の日本人面接官への回答については、自信がありません。
これは、事前に考えたけれど、自分なりの答えが充分に見つから
ないままに当日を迎えてしまった感じです。
今回二次試験まで初めて進み、自分で自信の持てる分野、趣味、観 光地などを多く持つことがいかに大切かを感じました。
そこから、本物の感動や気持が前に出て、相手に伝わるのではと
思いました。
ページトップに戻る▲
次の受講生のレポートを読む>>
|