| <<一覧に戻る | 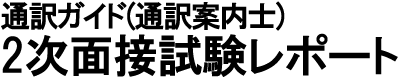
受講生46(1)試験会場到着から試験室入室までの手順 試験会場(立命館大学衣笠キャンパス 清心館)到着後、受付開始時間(10:00)まで1階の学生談話室(飲料の自動販売機なども設置したラウンジ、当日学生は不在)で待機、受付時間の10:00に係りの方の案内で順不同でエレベータで4階の大教室へ移動、教室前のホールの受付で「○-△(○グループの△番)のネームタグを受け取り、指定された席に着席(13グループ×6名)。 (2) 試験官の性別、推定年齢、国籍
外国人:45才くらいの男性(終始笑顔で対応してくれました) (3) 自己紹介等のウオーミングアップのやり取り
着席後、氏名と住所を聞かれました。 (4) 通訳の日本文(たまたま同じ時間帯に受験の知人にも確認しました) (5) 英語訳の再現回答全文は記憶が定かではありませんが、ちりばめた単語は以下の通りです。 donjon castle tower fortress load(the load of a castleとはいえませんでした) symbol power などです。 (6) プレゼンテーションの3つのトピック
1.日本の自然災害について (7) 選択したトピック1.日本の自然災害について (8) プレゼンテーションの再現(英語はご容赦ください) (9) Q&Aのやり取りの再現(要旨) 曽根先生のアドバイスに従い、外国人観光客に案内するような雰囲気で質疑応答は進みました(ネイティブの試験官は終始にこやかでした、この間、試験直前の数日間、盆栽展、伝統工芸館、京都タワー展望台、国立京都博物館などで機会を作って外国人に説明するなどロールプレーを意識して取り組み、通勤途上に駅などで観光客に道案内をすることや、質問にも(説明内容の正確性はともかく)積極的に対応することをしてきましたので、自然と対応することができました)。 (10) 日本語での質疑応答の有無ありませんでした。 (11) 試験終了後のやり取り最後にThank you very much for this great opportunity, thank you ありがとうございましたと言って 退出しました。 (12) 終了後、退出してから解散までの手順同じ時間帯・同一フロアで受験した④のメンバーがそろってから、待合室とは別の教室で最終の受験者の面接が終わるまで待機(実際には、最終の組が入室してからも解散されず、受験案内にあった12時15分きっかりに)解散となりました。 (13) 全体を通しての感想などプレゼンテーションの後の質疑応答への対応も含め、それぞれのトピックに関して、知識だけでなく自分自身の体験を踏まえ、対応できるよう広範なトピックへの「引き出し」を準備することの重要性を再認識しています。 ありがとうございました。
|